トップページ > 暮らし・手続き > 地域活動・コミュニティ > 千代田区町名由来板 > 町名由来板:町名から探す > 町名由来板:神田佐久間町二丁目(かんださくまちょうにちょうめ)・神田平河町(かんだひらかわちょう)
更新日:2025年3月26日
ここから本文です。
町名由来板:神田佐久間町二丁目(かんださくまちょうにちょうめ)・神田平河町(かんだひらかわちょう)
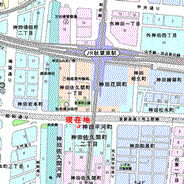
- 設置年月日:平成16年1月21日
- 所在地:神田平河町1番地

この界隈(かいわい)は、江戸時代の早い時期から商人や職人が集まる町でした。「佐久間(さくま)」の町名は、佐久間平八(さくまへいはち)という材木商が住んでいたことから生まれたと伝わっています。江戸時代初期の慶長(けいちょう)年間(1596年~1615年)、江戸城築城のための材木を供給したのも佐久間町でした。古くから幕府に仕えた町ということで、将軍家に祝い事があるときは町人たちにも能の見学が許されていたといいます。
古い資料を見てみると、この界隈から火事が頻発していた記事が数多く残されています。文政(ぶんせい)十二年(1829年)には、神田だけでなく両国橋(りょうごくばし)から築地(つきじ)、佃島(つくだじま)、本銀町(ほんしろがねちょう)あたりまでを焼き尽くした大火の火元となりました。また、天保(てんぽう)五年(1834年)にも、江戸市中を焼いた火事が佐久間町から発生しています。
江戸時代から続いた神田佐久間町二丁目は、たび重なる火災で町が南北に分断されていましたが、明治二年(1869年)にその間の武家地を編入しました。明治四十四年(1911年)、いったん神田を取って佐久間町二丁目と改称しましたが、昭和二十二年(1947年)には、その名を昔ながらの神田佐久間町二丁目に戻し、現在に至っています。
一方、神田平河町(かんだひらかわちょう)も、防災と深いかかわりをもった町です。享保(きょうほう)十二年(1727年)、防火のための火除地(ひよけち)が麹町平河町一丁目(こうじまちひらかわちょういっちょうめ)に設けられました。そこに住んでいた人々のための代地(だいち)が神田佐久間町の隣に置かれ、麹町平河町一丁目(こうじまちひらかわちょういっちょうめ)代地と呼ばれたのです。その後、明治二年に神田平河町(かんだひらかわちょう)、明治四十四年には平河町と名を変えましたが、昭和二十二年になると、再び神田平河町と改名しました。
お問い合わせ
地域振興部コミュニティ総務課コミュニティ係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4180
ファクス:03-3264-7989
メールアドレス:komisoumu@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください



